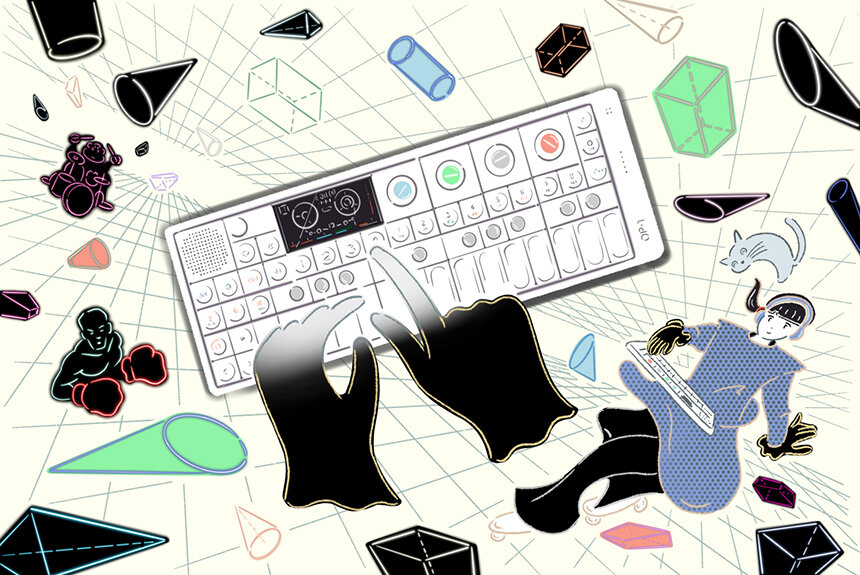シンセサイザーは私たちの生活に何をもたらしうるのだろうか?
「パンデミックにより社会はどんどん変わっている。デモも起こってるわ。取り組むべき問題がたくさんあるのは明白よね。だからこそアーティストやーーマイノリティーの人々や女性に参加してほしい。このマシンは未来の音を生む。みんなが未来の声を生んだらどうなるかしら」
Apple TV+で公開されている『サウンドを語る with マーク・ロンソン』(2021年)のなかで、シンセサイザー歴史家のエミー・パーカーは視聴者にこう語りかける。「このマシン」というのは、シンセサイザーのことだ。
そしてこのパートで番組がフィーチャーしているのが、スウェーデン・ストックホルムを拠点にする電子楽器メーカーTeenage Engineeringが2011年に発表したOP-1というシンセサイザーである。
シンセサイザーとともに日常を送っている人はそう多くはないだろう。だが、あえてこう問いかけてみたい。私たちにとってシンセサイザーとは何か?
番組のなかで、ホストであるマーク・ロンソンは「素人レベルのミュージシャンをプロに変えてしまう」ものだと語り、エミー・パーカーは「自由のためのツール」と表現し、ケヴィン・パーカー(Tame Impala)は「電気の箱(シンセ)を通して自分の世界を表現できる」と語る。
言葉にしがたいものを表現するために、絵を描いたり、写真を撮ったり、詩を書いたりする……シンセサイザーで音をつくり、鳴らすという行為は、そういった営みと本質的には同じことであり、シンセサイザーは人々の心のうちに眠るクリエイティブなエネルギーを解放するものだーーこの番組からはそんなメッセージを受け取ることができるように思う。

SNS時代に増加するアマチュアミュージシャンとメンタルヘルス
SNSに動画を投稿できるようになったことで、自らのベッドルームから音楽を発信するアマチュアのミュージシャンが増えている。エミー・パーカーはこう指摘し、SNS時代を象徴するシンセサイザーのひとつとしてOP-1を紹介している。
@op1andchillより
「@op1andchill」は、ホームスタジオで録音して日常的に音楽を発表するミュージシャンたちの動画をキュレーションしてシェアするInstagramアカウントで、「#OP1」のハッシュタグをつけた投稿は10万件以上にものぼる(2021年12月現在)。
@op1andchillでシェアされる投稿のなかには、アンビエントや実験的なエレクトロニックミュージック、そしてローファイヒップホップ(別名、チルホップ)と呼ばれるものも少なくない。
非常にシンプルかつ予定調和的で「誰にでもつくれる」としばしば指摘されるローファイヒップホップは、「特に若年層の抱える社会的ストレスを開放する手伝いをしている」という言説もあり(※1)、アマチュアミュージシャンの増加と照らし合わせて考えると興味深い。
※1:HYPEBEAST.JP『カルト的に支持される“ローファイ・ヒップホップ”の人気の秘密を探る』参照(外部サイトを開く)
ローファイヒップホップに限らず、オノ・ヨーコが「Art is a way of survival(アートは生存方法だ)」という言葉を残しているように、SNS時代に増加するアマチュアの音楽家たちは、「音楽をつくる」という行為を通じて、自らのメンタルヘルスのケアをし、ストレスフルな社会を生き抜く糧を得ているのではないか。
当然、それはOP-1以外の楽器にも当てはまることだが、マーク・ロンソンが「装置はアナログなのに現代のシンセ時代に適応している」と番組で語ったように、このSNS時代において、ユーザーの創造性と可能性を限りなく刺激する楽器でありながら、おもちゃのように手軽に扱えるというOP-1の優位性は特筆すべきだろう。
OP-1がミュージシャンに愛される理由。三船雅也とKuroがその出会いを振り返る
星野源やBon Iverのアルバムでも使用されるなど、OP-1を愛用しているのはアマチュアのミュージシャンだけではない。
音楽家たちに幅広く愛される理由はどこにあるのだろうか? その具体的な特徴や魅力を考えるにあたって、楽曲制作やライブでOP-1を使用する三船雅也(ROTH BART BARON)、Kuro(TAMTAM)に協力してもらい、アンケートを実施した。
まずはふたりにOP-1との出会いについて振り返ってもらおう。
三船:おそらく2016年の自主イベント『BEAR NIGHT』でアリー・モブスに教えてもらったのが最初の出会いでした。彼は京都在住のトラックメーカーで、おもちゃのような楽器やコントローラーを自分でつくってしまう、とても面白いアーティストなんです。
三船:彼とオンラインゲームにどハマりしていたときがあり、そしたらアリーのゲーム友達がTeenage Engineeringで働くようになり、彼に本気で勧められたのがOP-1を手にしたきっかけです。その楽器とは思えない可愛らしいキャンディのような見た目、遊び心にひかれてしまいましたし、強いご縁を感じたので。

シンガーソングライターの三船雅也が2008年に結成した日本のインディーフォークバンド。これまでに4枚のEP、5枚のオリジナルアルバムを発表している。2021年12月1日には4年連続リリースとなる6thアルバム『無限のHAKU』をリリース、全国ツアーを開催する。
Kuro:2014年頃、Dirty Projectorsというバンドがラジオライブ出演時の小編成で使用しているのを見たのがOP-1との出会いですね。音色とボディのデザイン双方に一目惚れし、即購入しました。バンドのライブでもずっとメイン機材としてOP-1を使用しています。

北海道出身。シンガー、ソングライター、プロデューサー、トランペットやシンセを扱うマルチ奏者であり、東京で活動するバンドTAMTAMのメンバー。2019年9月発売の1stアルバム『Just Saying Hi』より本格的にソロでの活動を開始。EVISBEATSとのコラボを始めとし、以降さまざまなミュージシャン / トラックメイカーとの共作を行う。
ふたりが共通して指摘するように、OP-1の最大の魅力のひとつはシンセサイザーの難解そうなイメージとは裏腹の可愛らしく遊び心のある見た目だ。
IKEAとコラボして段ボール製のデジタルカメラ「KNÄPPA」(2012年)を発表するなど、遊び心のある発想とそれを具現化する優れたデザインは、Teenage Engineeringのお家芸。ユーザーに対して壁をつくらないデザインは、幅広いミュージシャンに愛される要因にもなっていることだろう。
ちなみに、このどこか有機的で温かみも感じさせるプロダクトデザインは北欧デザインを思わせるが、Teenage Engineering代表のイエスパー・コーフーは「スカンジナビアのデザインは退屈に思えて好きではありません」と笑いながら明かしている(※2)。
※2:Rock oN Company『スウェーデン現地取材 teenage engineering 代表 Jesper Kouthoofd 氏インタビュー』参照(外部サイトを開く)
遊び心に溢れた多機能性で、OP-1はユーザーのクリエイティビティーを掻き立てる
OP-1の魅力は当然、デザインだけではない。ふたりはどのようにOP-1と向き合い、どんなふうに刺激を受けているのだろうか。
三船:UI / UXがとにかく優れていて直感的にサウンドをつくれるよう、よく考えられています。触れば触るほど楽器を理解できるようになるんです。
三船:つまむ、ひねる、押すといった指先のシンプルな動作がしっかりと音に反映されるーー脳と指先と楽器が無駄なく呼応してくれるのはAppleのiPhoneと似た哲学を感じますね。
エフェクト、ビートマシン、レコーダー、サンプラー、シンセ、そのすべてが新しい想像を掻き立ててくれるんです。制作で悩んだら子どもの頃の気持ちに戻ってOP-1を触っていますね。いつもスタジオやツアー、飛行機に持ち込んで思い立ったらすぐアイデアをスケッチできるようにしています。
Kuro:私の場合、ほかのシンセサイザーを触るときは「どんな音が欲しい」が先に頭のなかにあってそれを目指すことが多いですが、OP-1の場合はなにも目標を立てず、行き先を決めずに、テキトーにパラメータをいじっているときが一番楽しいです。どこかで聴いた音色を再現するのにはあまり向いていない楽器かもしれません。
プリセットの音色がユニークで一癖あるのもいいところです。自宅ではOP-1のみでデモをつくる機会も多いですが、それは私が作曲段階では質の高さよりもユニークさを求めていて、OP-1がそれを助けてくれるからだと思います。思いもよらない音色が楽曲のフックになったり、アイデアをくれることはよくあります。
また、家だけでなく旅先など外で作業したいときもOP-1とMacbookだけは必ず持っていって、思いついたらすぐ触れるようにしています。
1台だけでもパフォーマンスを完結させられる多機能性、さまざまな機能やエフェクトを組み合せて思いもよらないサウンドに直感的に出会うことができるユーザビリティーの高さ。大きくこの二点がOP-1というシンセサイザーの魅力と言っていいだろう。
では、実際にふたりはOP-1をどのように使って創作しているのだろうか。
三船:ぼくはこの楽器をギターの次に持ち歩いているので、例を挙げたらキリがないです(笑)。OP-1がなかったらROTH BART BARONのサウンドはまた全然違った未来になっていたのかもしれません。
“極彩 | I G L (S)”の声のサンプリング三船が送ってくれたOP-1を用いたROTH BART BARONの楽曲リストとプレイリスト(Spotifyを開く)
“けもののなまえ”の浮遊感のあるシンセサウンド
“TAICOSONG”のビットクラッシュしたドラム
“000BigBird000”のサンプリングサウンド
“Special”のイントロのツンザクような金属音
Kuro:TAMTAMのなかで使ってない曲はほぼないと言っていいと思います。
なかでも多用している音色は“Esp feat. GOODMOODGOKU”のイントロやサビ、“CANADA”のサビなどで使っている音色(どちらも同じもの)です。これらはOP-1で音色を自作し、コードを弾いてトラックのベーシックをつくりました。
音色に存在感があるので、デモで使用するとそのあと他の楽器に置き換えられなくなりがちです。同じように、もし私のOP-1が故障したら、ライブ時にほかのシンセで代替することは難しいでしょうね。それくらいTAMTAMにとってシンボル的音色です。
10年前に発表されたOP-1が、いまなお最先端であり続ける理由
2011年に発表されたOP-1は、OSのアップデートによって新しい音色や機能が追加・拡張され続け、完成されることなく進化を重ねている。懐かしくも未来を感じさせるOP-1に「2020年代らしさ」、あるいは先鋭性を見いだせるとしたら、それはどんなところだろうか?
三船:サウンドの解像度的には正直言って10年前感、古臭さがある印象です。音の出力もこもっていますし、非力です。
しかしOP-1にしかない魅力がたくさんあるのもまた事実です。iPhoneが写真やビデオという概念をここまでみんながアクセスしやすいものに変えたように、OP-1はシンセサイザーをぼくらの生活の身近なツールに変えた、静かな伝説のような楽器です。こんなに遊び心があってワクワクさせてくれるものはなかなかありません。

三船:新しいものを毎年出し続けることがいいことなのでしょうか? 一瞬でバズって翌日には誰も覚えていない、価値がどんどん下がってしまう泡のようなものをつくるより、10年間変わらず愛されるいいものを生み出すことはもっと難しいはずです。
購買者を飽きさせないために次々と新しいものを生み出しドーピングしてゆく、資本主義のアイデアとはまったく逆のアンチテーゼを持ったこの楽器のコンセプトこそが非常に2020年代的だと思います。
Teenage Engineeringのプロダクトにはまずデザインがあります。よいデザインはシンプルに暮らしや心を豊かにしてくれます。デザインの行き届いたもので音楽をつくることは、ぼくの心も豊かになって気持ちがいいです。これからもOP-1を世界中に持って行ってたくさん音楽をつくりたいですね。
Kuro:好きなところ、すごいところはたくさんありますが、アナログモデリングのシンセ(※3)をあの携帯しやすいサイズで実現しているシンセは、2021年になる今でもほかに例が思い当たりません。
そのうえで、4つのつまみだけである程度の機能が楽しめるシンプルさと、逆にやり込み要素もある奥深さ。それらがOP-1をさまざまな人にひらけた楽器たらしめているポイントです。
機能は深くても操作性の面でユーザーを選ばず誰もが楽しく扱えることから支持を得ているモノは現代において多く思い当たりますが、シンセサイザーの世界でいち早くそれを目指したのがTeenage Engineeringだったんじゃないかと思います。
※3:トランジスタなどで構成された電子回路で電気的に音を生み出すアナログシンセサイザーのサウンドを、デジタルで再現するシンセサイザーのこと
Kuro:あとは、公式ではないですがop1.funという個人がつくったコミュニティーサイトがあり、サンプル音源をフリーダウンロードできます。Teenage Engineeringがそういうやりとりを許容してるのも、いまっぽいと思います。
世界中の創造的ユーザーが、OP-1を「現代の名機」にした
OP-1はそのポップな見た目、シンセサイザーの伝統をあえて踏襲しない遊び心に溢れた筐体とUI / UXから、「楽器か、おもちゃか」という議論が発表当初から存在していた。当然、見解は分かれるところだろうが、ここでは歴史上最も著名なリズムマシンRoland「TR-808」の開発者、菊本忠男が語った哲学を引用しよう。
「器を作るのはメーカー、楽器にするのは天才アーティスト、名機にするのは創造的ユーザー」(※4)
これほどまでに創造的ユーザーに恵まれた、あるいは幅広いユーザーのクリエイティビティーを刺激するOP-1を、「現代の名機」と言ってもきっと差し支えはないだろう。
※4:DU BOOKS『ベース・ミュージック ディスクガイド BAAADASS SONG BASS MUSIC DISCGUIDE』参照(外部サイトを開く)
個人のベッドルームで、シンセサイザーやリズムマシンを、あるいはラップトップを使った制作、音楽活動が特別なことではなくなったのは、最近の話ではない。マシンを用いて個人の表現を具体化できる可能性がより広がったのは、デトロイト・テクノが勃興した1980年代後半だ(※5)。
録音技術の発達、安価化によって誰でも録音ができるようになったことは、つまらない音楽が氾濫する要因にもつながったという指摘も存在しているが、より多くの人が自らのクリエイティビティーを発揮する機会を得ることこそがTeenage Engineeringの目指すところだろう。本稿ではその視点を重視したい。
※5:JICC出版局『クラブ・ミュージックの文化誌―ハウス誕生からレイヴ・カルチャーまで』(1993年)参照
ビョークやAviciiら世界的音楽家だけでなく、優れた電子楽器メーカーも輩出する北欧諸国
Teenage Engineeringを輩出した北欧とエレクトロニックミュージックのあいだには、長く、そして深い関係が存在している。
ビョーク(アイスランド)やAvicii(スウェーデン)を筆頭に、Pan Sonic(フィンランド)、トッド・テリエ(ノルウェー)、MØ(デンマーク)、近年ではSmerz(ノルウェー)など、ワールドワイドに活躍する北欧出身の音楽家やDJは珍しくない。
ポップスから実験音楽、EDMやディスコなどクラブミュージックまでをもひと括りには語れないが、ここで着目したいのは、北欧にはTeenage Engineeringのほかにも有力な電子楽器 / 音響メーカーも数多く存在していることだ。
トム・ヨーク(Radiohead)やAutechreによる使用でも知られ、テクノ / ハウスやヒップホップをはじめビートミュージックのシーンで絶大な信頼を得るシンセメーカーのElektron(スウェーデン)、レコーディングスタジオでも使用されるモニタースピーカーのメーカーであるGenelec(フィンランド)、大学の軽音サークルからプロの第一線の現場まで幅広く愛用されるシンセサイザーで知られるNord(スウェーデン)、ミニマルなデザインと環境に優しくサステナブルなプロダクトで知られるオーディオメーカーAIAIAI(デンマーク)などなど……世界中にユーザーを持つ電子楽器 / 音響メーカーが北欧にはいくつも存在している。
自ら何かを創造する行為、誰かのクリエイティビティーを解放する手助けになる優れたプロダクトを生み出すこと、あるいはひたすら高品質のものを追求するものづくりの姿勢ーー北欧諸国に根づくクラフトマンシップの精神と、これらの電子楽器 / 音響メーカーの存在は決して無関係ではないだろう。
シンセサイザーは、すでに私たちの生活に身近なものとして存在している
シンセサイザーは、かつてイメージされたような、難解で、目が飛び出るほど高価で、限られた人のために存在する機械ではない。OP-1は10万円ほどするものの、Teenage Engineeringは1万円前後で手に入る安価だが興味深いPOシリーズというプロダクトも発表している。
そして何より、あなたがもしこの記事をiPhoneで読んでいるとしたら、すでにシンセサイザーを手にしているとも言える。iOSアプリ「GarageBand」を開いて10分も触っていれば、iPhone内に存在していた無数のシンセサウンドに出会うことだろう。
知らず知らずのうちに無数の人々がその手のなかに、音楽をかたちづくり、発表できる可能性を持ち歩いているーーいまはそんなことがすでに当たり前になった時代だ。
音楽を制作する人が増えれば増えるほど、音楽文化そのものの可能性は広がり、エミー・パーカーが語ったように「未来の声」が至るところで生まれるようになれば、この世界は少しずつ変化し、豊かになっていくことだろう。
きっと手段やツールは何でもいい。そして、シンセサイザーはそのもっとも身近な選択肢のうちのひとつなのだ。