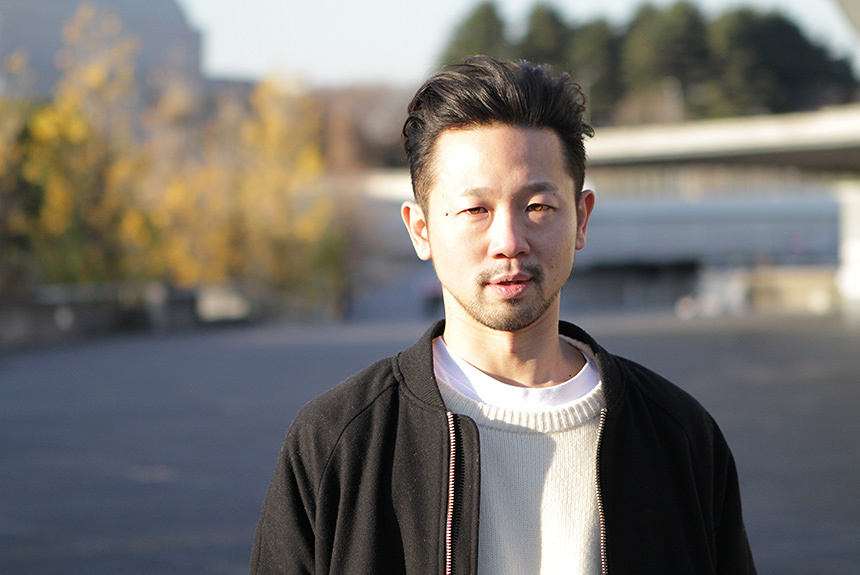持続可能な都市の構築を目的としたスマートシティ化が、世界的なムーブメントになっている。そのパイオニアとも言われているのが、北欧諸国デンマークの首都コペンハーゲンだ。古くからの街並みが数多く残るこの地では、2025年までに二酸化炭素の排出量を減らし「カーボン・ニュートラルを達成する世界で最初の首都になる」という目標を掲げ、美しい景観はそのままに、街のエコ化、サスティナブル化を推し進めている。コペンハーゲンでどのような都市づくりが行われているのだろうか? 建築家・藤本壮介氏のもとで設計を学び、コペンハーゲンに活動拠点を移した建築家、加藤比呂史さんに話を聞いた。
北欧に来てから、労働時間の対価としてではなく、思考の対価として給料をもらっているんだなと考え方が変わっていった。
—加藤さんはデンマークを拠点に活動されていますね。なぜコペンハーゲンで建築の仕事をしようと考えたのでしょうか?
加藤:日本と180度違う場所に行って自分を試してみたかったんですよね。なんか面白いじゃないですか、自分と同じ人間がまったく違う環境で生きているのって。だから、本音をいえば日本じゃなければどこでもよくて、当初はアメリカのカリフォルニアかスイスのバーゼルに行こうと思っていたんです。でも、たまたまデンマーク人の知人と縁があって、移り住んでしまったんです(笑)。
ぼく、曲がってる道が好きなんですよ。その先に何があるのか予測がつかないから。もしかしたら、そこには知らない誰かの日常や、自分のまったく知らない世界が広がっているかもしれませんよね。それはぼくにとっての非日常ですし、それらとの出会いによって人生が変わるかもしれない。そういう未知との出会いを求めて、予定調和を避けながら進んできたところはありますね。
—コペンハーゲンでは「COBE」(アディダス本社など商業建築のほか、多くのパブリックスペースを手がける北欧の気鋭の建築事務所)に在籍されていたそうですが、そこでの活動を通じて変化したことってありますか?
加藤:まず仕事に対する考え方がガラリと変わりました。日本にいるときは、とにかくがむしゃらに働いて、それが楽しかった。世のなかで話題になるプロジェクトにも数多く関わることができたし、プライベートな時間もいらないくらい仕事に熱中してました。でも、デンマークに来たらいきなり17時に仕事を終えるような生活になったんです。というのも、みんなその時間になると帰ってしまうから。
—日本だと建築家は激務のイメージがあります。
加藤:デンマークの人たちは、「長時間働けば、それだけ体も疲れるし、ストレスも溜まる。そんな状態では良い仕事はできない」っていう発想なんですね。ぼくは日本で働いていた感覚が残っていたので最初は20時くらいまで働いていたんです。ただ、そうすると次の日は通常よりも早く仕事を切り上げて帰らなくてはいけないルールだったので、結局仕事に費やせる時間の総量は変わらないんですよね。なので徐々にデンマーク流の働き方にシフトしていきました。
すると、横になっているときとか、シャワーを浴びているときとか、仕事をしていない時間に良いアイデアが浮かぶようになってきたんです。そこではじめて、コンディションを良い状態を保つ重要さに気づきました。労働時間の対価としてではなく、思考の対価として給料をもらっているんだなと考え方が変わっていきましたね。
時速5kmで歩いて街を回るのと、自動車に乗って時速60kmで回るのでは見えてくる街の景色は大きく変わります。
—現在、加藤さんはコペンハーゲンを拠点に個人で活動されていますが、この都市の魅力はどんなところですか?
加藤:街のサイズが丁度いいですよね。すべてがコンパクトなんですよ。友達とご飯を食べようと思ったら、街のどこにいても30分くらいで会える距離感。しかも自転車で移動できる距離だから、終電の時間を気にする必要もない。日本で考えると福岡市に近いかもしれないですね。
—コペンハーゲンは世界でも有数のサイクリング都市で、市内には自転車専用レーンがあると聞きました。
加藤:最初は驚きましたね。朝の通勤時間とかは自転車だらけで特にすごい。みんな、雨が降っていても乗ってますし。なので、自分の自転車が盗まれたりすると、自分だけ街のスピードについていけない感覚を覚えます。小学生の頃に、まだ自転車を持っていない子が自転車に乗った友達を走って追いかけることってあるじゃないですか、あの感覚に近いです。ぼくは自転車も好きですが、いまはスケートボードの移動にはまっています。自転車と同じぐらいのスピードで移動できるし、そのままバスや飛行機にも乗ることもできる。長くなるので、この話題は別の機会にしましょう。

東京でもスケボーで移動することが多いと話す加藤さん。移動手段を変えることによって街の違った側面が見えてくるという
—どうしてそこまで自転車の普及が進んでいるのでしょうか?
加藤:それはヤン・ゲールという建築家の功績が大きいんですよ。彼が「脱・自動車」を掲げ、歩行者を中心とした都市計画を打ち出したことですべてが変わりました。コペンハーゲンは「時速5kmシティ」って呼ばれているんですよ。時速5kmで歩いて街を回るのと、自動車に乗って時速60kmで回るのでは見えてくる街の景色は大きく変わります。当然、時速5kmの方がいろいろなものが見えてくる。だから、街の風景もきめ細かに作らなきゃいけないという思想が市民の間にも根づいているんだと思います。
—では、自動車に乗っている人は多くないのでしょうか?
加藤:もちろんいることはいますが、自動車を使っても一方通行ばかりで目的地になかなかたどり着けないですし、自転車のほうがやはり移動しやすいのではないでしょうか。それにコペンハーゲンの街中では、極力自動車を排除しようとしている動きがあります。自転車100台と自動車100台だと占有する面積が大きく変わりますよね。街をあげて自転車利用を促進し、空いたスペースを公共利用したりしていますね。
ぼくが在籍していたCOBEが関っていた「Nørreport Station」のリニューアルも、まさにその発想が根本にあって。駅自体は地下にあって、地上部分は大規模な駐輪場として活用されているんです。こういう場があることで、コペンハーゲンに住む市民のアクティビティが活発化して、結果として周辺地域にプラスの影響を与えることができるんです。

Nørreport Station。最大で2,500台の自転車を停めることができる
—そういった都市づくりに対する意識の差が、日本とデンマークではまったく異なるように感じます。
加藤:例えば、自由競争のある国では地価の高い場所は公共スペースになる確率ってかなり低いですよね。おそらく日本だとオフィスビルが立ち並んで、コンビニがそこかしこに乱立する状態になると思います。でも、デンマークのように高い税金が設定されている国ではそうはいかない。対価としてそういう場所も市民に開放されるんですよ。だから「Nørreport Station」のような場所も、ある一定の統率が取れた状態で形成されていくんです。
エコって「愛」だと思うんですよ。1つのものを大切に、長く使い続けることで、そこから何度も価値を享受することできる。
—そうした市民の目が厳しい環境で、建築の仕事に携わることの難しさはあるのでしょうか?
加藤:意外かもしれませんが、逆に日本よりも進めやすいと感じますね。公共性のある建物の場合、政治家がうまく辻褄が合うようにプレゼンし、それを市民の9割が納得すれば成立してしまうので。だからこそ、意外性のあるものが生まれにくいという側面もあります。ある意味で85点の建築が多いんです。クオリティーが低いわけではないんだけれど、突き抜けるものがないっていう。
建築家としては、やはりそのことへのジレンマはあります。日本だと個人の表現が重要視されているから、有名建築家が手がけた建物ってまるでアートピースのように扱われますよね、それが良いか悪いかは別として。120点を取れるときもあれば20点のときもある。その結果として特異性が生まれると思うんですけど、そういうものがコペンハーゲンにはほとんどないんです。計画的だからこそ、セレンディピティが生まれない。そこは一長一短があるかな、と。

『Weaving Between』。2017年夏、京都芸術センターにて発表された影でつくられるランドスケープのプロジェクト。校舎と校舎のあいだに張られたテープに夏の日差しが注ぎ込まれ、校庭全体に織物の様な影を落とす。©KATO Hiroshi
—コペンハーゲンに住む人のデザインリテラシーの高さは感じますか?
加藤:どうなんでしょうね。個人的にはではリテラシーが高いというよりは、コンサバティブな印象が強いです。過去につくられた価値あるものがたくさん残されているので、それを守ろうとしているんだと思います。あとメンタリティの問題になりますが、サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートの意識が強い人が多いかもしれません。デンマークって日本に比べると日照時間が短いから、とにかく太陽の当たるところが好きなんです。夏場とかになるとビキニになって外出している人とかもいるくらいですし。
—デンマークと比較して、日本の都市づくりに欠けているものがあるとすれば何でしょうか?
加藤:元々あるものに対し、どういう価値を足していくかという思考が日本の都市づくりには欠如しているように思います。その結果として、どんどん都市としての個性が失われていき、どの街も同じような雰囲気の場所が生まれていく。
日本の都市って、駅ビルがあって、バスロータリーがあってというふうに、多くが駅を中心として栄えているじゃないですか。その設計の仕方って、見方を変えれば人の集まる場所を奪うことでもあるんですよ。そうした都市計画によって寂れていった商店街がいくつもある。ぼくとしては、もともとその土地が持っているポテンシャルを起点にして都市づくりをしていく方法もあると思うんですよね。
—コペンハーゲンだと古くからの街並みをベースに、部分的に新しくしていく傾向が強いんですよね。
加藤:日本ではそういう考え方をしない都市の方が多いですよね。スクラップ&ビルドの姿勢が強い。昨今の空き家問題とかもそれに似た性質がある気がします。だから、最近は解体と建築を一緒にできたらすごくいいなって思います。
—解体、ですか?
加藤:使えそうなものを活かして新しい建築をつくる、ということをしてみたいんです。例えば、バブル期の日本っていまでは考えられないくらい贅沢な作り方をしている建物がたくさんあるんですけれど、大抵は壊して終わりです。それを負の遺産として捉えるのではなく、1つの価値あるものとして未来に繋いでいく方が面白いんじゃないかなって思うんですよ。それってすごくエコじゃないですか?
—確かにそうですね。
加藤:ぼく、エコって「愛」だと思うんですよ。1つのものを大切に使うと、長持ちするじゃないですか。長く使い続けることで、そこから何度も価値を享受することできる。そうした結果、無駄なものは減っていきますよね。
でも、エコって、それ自体を目的化しちゃいけないんです。「地球のために」ではなく、面白いことを考えた結果として大切にされ、長く使われていく。そうしたかたちでエコにつながることがしたいんですよね。
東京は1人あたりが使える土地の範囲が狭いから、都心の人々が開放的な場所に出向く習慣をつくることが大事だと思うんです。
—デンマークの都市づくりから日本が見習うべきことあるとすれば、どのようなものがあると思いますか?
加藤:公共スペースの使い方とかは参考になると思います。日本人って「みんなのものは丁寧に使わないといけない」という意識が強すぎる気がするんですよね。結局、ほとんどの人は使わず、ある特定の人だけが使うものになってしまう。
コペンハーゲンの人は良い意味で図々しくて、傷ができたらそのときに考えれば良いという意識でうまく公共空間を利用しているんです。以前僕らが設計したパルクール場なんかはまさにそう。学校の跡地を活かして作られているんですけれど、みんな遠慮せずに使ってくれている。そういうおおらかさが日本人にはもっと必要なのかなって。

『Slngerup』。コペンハーゲンから車で30kmほどの街ある中学校で設計したランドスケープのプロジェクト。スケートボードパークを中心に、あらゆる子供が楽しめる様なスペースになっている。

『Slngerup』©Rasmus Hjortshøj

『Copenhagen Dream』。コペンハーゲンの街に提案している、新しいかたちのパブリックスペース。デンマークの家庭には、ウインターガーデンという温室の庭をつくるという習慣がある。アパートメントブロックの隙間にウインターガーデンを設置し寒い冬も町の至る所に逃げ込める暖かい場所を生み出すプロジェクト。©KATO Hiroshi + Ramboll
加藤:でも、デンマークが日本から見習っていることもあるんですよ。コペンハーゲンって中庭があるようなロの字型の建物が多いから、けっこう空き地が多かったりするんです。そういう狭い場所を有効活用するのに日本人的な発想がけっこう役立っていて。東京って特に土地が狭いじゃないですか。そういう場所でもうまく使えるのが日本人の良いところです。
ぼくはそういったなんとも定義しづらいようなスペースに、新たなアクティビティーを持ち込むことができたら良いなと考えています。コペンハーゲンにあるニュー・カールスベア美術館が週に1回、パブリックに開放されているんですね。特に冬とかは寒いから、そういう場所に市民が集まったりするんです。そういう取り組みが市内にもっと増えれば、家族でも住みやすくなるから人口も増えるし、それによって雇用も生まれ、街の雰囲気がもっと賑やかになっていく気がするんですよね。
—そういった場所は東京とかにあっても面白そうですね。
加藤:そうですね。ただ、そういう場所を市民がうまく使うようになるためには、生活に余裕がないとできないんですよね。特に東京なんて、長い人だと1日に往復で2~3時間ぐらい満員電車に揺られながら通勤してるわけでしょ。気が狂わないほうがおかしいぐらいなのに、みんな感覚が麻痺していて、特に何も思わなくなっている。
—確かにそうかもしれません。
加藤:そういう異常なところって、一度離れてみないとわからなかったりしますからね。ぼくは日本を一度離れたことで、そういうところに対して正直になっちゃったんです。満員電車って毎日乗ってると慣れてきちゃうんですけど、無意識のうちにストレスが溜まっていくと思うんですよ。だから、本当はもう少し人を東京から分散させるべきだと思うんですよね。
—地方に引っ越すというようなことですか?
加藤:それもありますが、実際には全員がそうすることは難しいですよね。とにかく東京は1人あたりが使える土地の範囲が狭いから、都心の人々が開放的な場所に出向く習慣をつくることが大事だと思うんです。それは必ずしも生活の場所を変えるという意味ではなくてもいい。
例えば、お墓参り。スウェーデンのストックホルムのはずれにエリック・グンナール・アスプルンドという建築家が築いた「森の墓場」という世界遺産があるんですけれど、そこの雰囲気がすごく良いんです。広大な森のなかに建築がうまく溶け合っていて、見事なまでのランドスケープで。併設された火葬場や礼拝堂も、じっくり時間を過ごすことが考えられた素晴らしい空間です。そういう環境を生み出すことが、日本にも必要なのかなって。
—おもしろいですね。「お墓」をただ故人を偲ぶ場所としてではなく、そこで過ごす人が心地よく過ごせる場所に変えるということですね。
加藤:そうですね。ぼくもお盆とかにお墓参りに行くんですけれど、正直いまの形式がもっとも好ましいのかと疑問なんです。狭いスペースに墓石がところ狭しと並んでいて、そういう場所で本当に故人と向き合えるのかなって思ってしまう。だったら、墓石と墓地の区画を購入するお金で地方の空気の良いところに小さな小屋を建てて、別荘として家族が集い、ご先祖様にお祈りをするという習慣に置き換えるのもひとつのあり方かなと考えたんです。親しい友人同士でその場所を共有するのも良いですよね。
お墓であれば、年に1回は足を運びますよね。毎年行く場所が素敵な場所になったら足を運ぶ意味合いも自然と変わると思うんです。1人が1平米持つという考えではなく、100人で100平米を持ち、使いたいときにその広さを活用するというような。そうやって、既存の概念を変えていけるものを、うまく実現していきたいですね。
- プロフィール
-
- 加藤比呂史 (かとう・ひろし)
-
1981年東京都生まれ。武蔵工業大学工学部建築学科(現・東京都市大学)卒業後に藤本壮介建築設計事務所に勤務。2010年にデンマーク・コペンハーゲンに渡り、ヨーロッパを中心にCOBE、KATOxVictoria、Rambøll、Tredje Naturなどで建築設計や公共空間のコンセプトディベロップメントに従事。現在はBeans.ltdにパートナーアーキテクトとして参加しながら、フリーランスアーキテクトとして活動を行なっている。