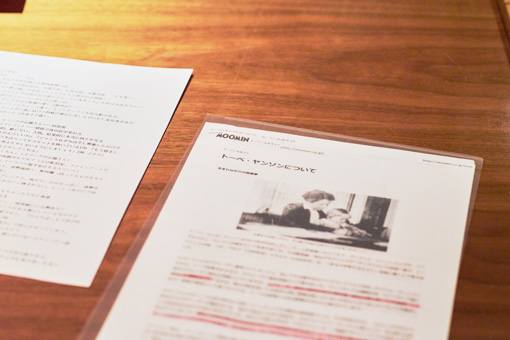「ムーミン」といえば、日本でもお馴染み、幅広い世代に愛されている元祖・癒し系のキャラクターだ。アニメや絵本などを通じて「ほんわか」した可愛らしいイメージが先行する一方、原作は読んだことがない、という人も非常に多い。それこそ「ほんわか」とは対極に映る、先鋭的な小説作品の翻訳を手がける岸本佐知子もその一人だったという。ところが実際に触れてみると……「今までごめんなさい、と謝りたくなるくらい興奮しました」と言う。
著書『罪と罰を読まない』(三浦しをん、吉田篤弘、吉田浩美と共著)では、読んだことのない作品を、巧みな想像力・妄想力で読み解いてしまう岸本。作品を読まずとも小説を楽しく読むことができる達人は、北欧を代表する作家、トーベ・ヤンソンの「ムーミン」シリーズをどう読むのか。翻訳家という職業柄か、たくさんの調べものをして取材に臨んでくれた。新たに発見したムーミンの魅力に始まり、その生みの親であるトーベ・ヤンソンの作風から垣間見える北欧文学の特色、そして翻訳小説の楽しみ方まで縦横無尽に語ってもらった。
私はやっぱりこういう孤独な人たちに心惹かれてしまいます。
―今回、北欧文学の中から岸本さんが選んでくださったのはトーベ・ヤンソンですね。なぜトーベを選ばれたのでしょう?
岸本:もともと彼女の作品は、いつかきちんと読んでみたいと思っていたのですが、なかなか読む機会がなくて。この機会にぜひ、と思い選びました。
私は「謎」が大好きなのですが、「謎解き」には興味がないんです。その点、トーベ・ヤンソンの作品は、ムーミン以外の小説に関しても言いっぱなしのままの部分があるというか、余白や余韻を残しているものが多い。短篇集『黒と白』(『トーベ・ヤンソン短篇集 黒と白』冨原眞弓=編・訳、ちくま文庫)にもすごく好きなものがたくさんありました。たとえば「砂をおろす」という冒頭の一編。
―わかりやすいオチがないというか、かなり変わった掌編ですよね。小さな女の子が肉体労働者たちの姿にひたすら見入ってしまう、ただそれだけのことがものすごく執拗に描かれている(笑)。
岸本:幼女が男たちの集団の中に入っていく図を想像すると、今の感覚だと危険というか(笑)、読んでいるこっちはちょっとハラハラしてしまう。
でも、この女の子には、とにかく強烈にいろんなものを見たい、全身で生きたくて生きたくてしょうがないという気持ちがあるだけ。それが、今を生きている子供の目で書かれているんですよね。そこがトーベ・ヤンソンのすごいところ。大人の目がぜんぜん入っていない。
―そういう、子供の頃の必死さがもたらす頓狂な事態が非常に細やかかつ鮮やかに書きつけられている点は、岸本さんご自身が編訳されている『コドモノセカイ』(河出書房新社)というアンソロジーなどにも通ずるものがある気がします。
岸本:そう! 『黒と白』の中の作品でいえば、たとえば「夏の子供」なんかはまさにそうですね。海辺の村でのどかに暮らしている一家のもとに、都会からやって来た意識高い系の子供が預けられることになるんですが、政治だのエコだの経済だの、小難しい話を空気を読まずに延々と語って聞かせようとするものだから、みんながうんざりしてしまう。
切なかったのが、その子が村の子と二人きりになったときに、初めて自分が嫌われていたことに気づく場面。あんなにウザいことをしていて、自分ではそれに気づいてなかったという……。
私はやっぱりこういう孤独な人たちに心惹かれてしまいます。他にも、まだ友達にもなっていないクラスメートたちに自分からつぎつぎ絶交を宣言していく「ルゥベルト」という掌編とか、もうめちゃくちゃ好きな一篇です。(笑)。
私、今までの人生でいちばん辛かったのは幼稚園時代なんですよ。
―岸本さんが惹かれるキャラクターに共通する部分ってどんなところなんでしょう?
岸本:やはり、自分の作りあげた脳内世界で完結しているがゆえに、外部と接触すると浮いてしまう点でしょうか。しかも自分では完璧な場所で生きているつもりだから、まったく自覚症状がないまま孤立してしまう。私はそういう人々を「はしっこの人たち」と呼んでいるんですが。
―自分のあずかり知らぬところでマイノリティー扱いされて、いつのまにかはしっこに追いやられてしまう。
岸本:そうです。トーベ・ヤンソンはフィンランド人なんですが、スウェーデン語を話す、フィンランド人の中でもすごく少数派の一人らしいんです。加えていえば、彼女の私生活における長年のパートナーは女性だった。そういう意味でもマイノリティーの視点は少なからず持っていたのではないかと思います。
―なるほど。そうした「はしっこ」の視点が、子供の目に映る混沌とした世界に複雑なリアリティを与えている、と。
岸本:子供の頃って妄想が止まらないじゃないですか。しかも妄想が実体化して実際に目に見えてしまったりする。でもそれを口に出すと途端に周囲から引かれてしまう。自分自身がそうだったからよくわかる。私、今までの人生でいちばん辛かったのは幼稚園時代なんですよ。
―なんとも早すぎる挫折!(笑)
岸本:外界と触れ合わず、自分が世界の中心だった状態から、初めて幼稚園という社会の中に放り込まれて、愕然としました。「自分は人間が向いていない」というのが、当時の切実な実感でした(笑)。しかもそれを矯正される過程がまた辛いんですよね。だから「ムーミン」の世界の、みんなが好き勝手やっても裁かれないあの感じには憧れます。
暗さや苦さこそが、この作者らしさなのかなという気がしています。
―ムーミンシリーズの中でも、今回岸本さんには『ムーミン谷の彗星』(下村隆一=訳、講談社文庫)を選んでいただきました。彗星が地球に向かってやってくることがわかり、生きものたちがパニックになるところから物語が始まります。
岸本:これ、シリーズものになることを意識してから書かれたムーミンの中では、いちばん初めに発表された作品なんですよね。なのに、いきなり地球が滅亡の危機に晒されてしまう(笑)。予想外にダークな出だしでびっくりしました。
―登場するキャラクターも、一般的に流通しているイメージとはちょっと違いますよね。
岸本:たとえばムーミンの友だちのスニフ。アニメの中でも、弱虫で臆病でめそめそしているキャラという印象がありましたが、原作だと五割増しくらいでウザい(笑)。
なんというか、けっこう俗物なんですよね。相手が自分より小さいか大きいかに異常にこだわっていたり、宝石が大好きだったり。
―何かが起きるとすぐ人のせいにしたり(笑)。
岸本:ムーミンママが用意してくれたケーキに、自分の名前が書いてないことにいじける場面がありますが、今まさに彗星がぶつかるぞっていう非常事態なのに、拗ねて外に飛び出して行ってしまう……。私はいじけキャラに同化してしまう傾向にあるので、イラッとしつつも何度も頷きながら読み進めていました。
―他のキャラも、完璧な善人というわけではけっしてない。
岸本:そう。ムーミンだっていかにも子供っぽくて自己中心的なところがあるし、スノークは仕切りたがり屋でやたらと会議をしたがるから、けっこうめんどくさいし。みんな欠点だらけなんだけど、でも誰ひとり「悪者」扱いされていないんですよね。
―なんだかんだ許されて受け入れられているというか。
岸本:あえて悪者として想定するなら、地球を壊そうとしている彗星なんですが、その彗星ですら作者は断罪せず、「ひとりぼっちで気が狂ってしまった星」という書き方をする。私、ここを読んでちょっと泣きました。
―トーベ作品の魅力でもありますよね。
岸本:この作品にも、やっぱり「はしっこにいる人たちの視点」が描かれていると思うんですよ。
―それが作品世界全体に漂うおおらかさにもつながる、と。
岸本:そうです。ついでにいえば、出てくる女性がどれも肝っ玉というか、どすこいキャラ(笑)。ムーミンママなんかその代表ですよね。たとえば家にあった鉢をパパが落として割ってしまっても、「いいのよ、あんなもの、割れてしまったほうが良かったのよ」なんて言ってぜんぜん動じない。とにかく大物なんです。
―ムーミンも信頼しきっていますもんね(笑)。
岸本:あの絶大なる信頼感はちょっと面白いですよね。パパが芸術家肌で実生活の役にはあまり立っていないぶん、しっかり者のママがぜんぶ切り盛りしているという関係性は、作者であるトーベ・ヤンソン自身の両親の姿に重ね合わせられるらしいんです。
トーベのお父さんは彫刻家で収入が安定しないぶん、グラフィックアーティストであるお母さんが商業的なイラストをバリバリこなして生活を支えていたそうです。そして芸術家一家だったから、変わり者の芸術家仲間がしょっちゅう家に出入りしていた。だからトーベは人間の造型には事欠かなかったと思います。そういう作家自身の背景も、ムーミン谷の仲間たちのキャラに反映されているのがよくわかります。
―この作品が書かれたのは、ちょうどフィンランドがソ連との長い戦争に敗れた頃だったんですよね。
岸本:そう、だから全体的にどことなく暗くて重たい空気が漂っている。シリーズ化が決まる前に書かれた最初のムーミン作品(『小さなトロールと大きな洪水』)は、洪水に追われてしまった一家がムーミン谷に住み着くというお話なんですが、洪水といえば『ノアの方舟』を連想させるし、どことなく旧約聖書を思い起こさせます。
また、新約聖書の「ヨハネの黙示録」には「ニガヨモギ」という名の星が落ちてきて、すべての川が苦く汚染されてしまい生きているものが滅びてしまうという記述があるのですが、これも『ムーミン谷の彗星』とよく似ていますよね。世界がどす黒くなって、海も干上がって生きものたちが打ち上げられてしまうんです。
このあとに書かれたムーミン作品はもうちょっと私たちの想像していたイメージに近いみたいですが、『ムーミン谷の彗星』にあるような暗さや苦さこそが、この作者らしさなのかなという気がしています。
―岸本さんが持ってきてくださった『トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界―ムーミントロールの誕生』(冨原眞弓、青土社)は、ムーミンの創作エピソードと併せてフィンランドの社会情勢について言及されている本ですよね。
岸本:『黒と白』をはじめ、彼女の作品をいくつも訳していらっしゃる冨原眞弓さんによる、とても面白い研究書なんですが、これを読んでいろんなことがわかって興味深かったです。「ガルム」というのはスウェーデンの雑誌の名前で、敗戦で苦しんでいたときに民族の怒りとか哀しみを風刺の形で代弁するような役割を担っていたらしいんです。トーベは15歳くらいからそこに挿絵を描いていたのですが、いつの頃からか、隅っこのほうにムーミンらしきものが登場するようになるんですよ。
―その頃から、ムーミンの原型が現れていたんですね。
岸本:トーベにとって、「ムーミン」という名前は最初は家に棲む魔物のことを意味するものとして記憶されていたらしいんです。昔、おじさんに「ストーブの裏にはムーミントロールという魔物が住んでいて、盗み食いをすると首の後ろにつめたい息を吹きかけるんだぞ」と脅されたんだとか。なにしろ寒い国に住んでるものだから、そのエピソードの印象は強烈だったらしい(笑)。
だから彼女の中では当初、「ムーミン」=「怖いもの、不気味なもの」というイメージだったようなんです。
―妖精、というよりは妖怪に近いイメージでしょうか。
岸本:だと思います。たとえば、彼女がドイツにいるおばさんの家に遊びに行った頃のこと。当時はナチス政権下にあって、みんな盗聴されているんじゃないかと怯えながら暮らしていた。そのときに描かれたムーミンは、黒いんです。人びとの不安を象徴するものとしてムーミンの絵を描いていたわけですね。
今は日本でも北欧ミステリーの人気が高くなっていますが、なんとなく、重苦しくて陰惨なイメージがありますよね。だから、今回ムーミンシリーズを読む前は、ムーミンやトーベ・ヤンソンの世界とはあまり結びつかないなと思っていたのですが、やっぱり共通している部分はあるんだなあと感じました。
翻訳家というのはラジオのようなもの。
―岸本さんは日本翻訳大賞の選考委員も務めていらっしゃいますよね。翻訳家という立場からご覧になったトーベ作品の魅力はどんなところにあると思いますか?
岸本:どれも描写がとても精密で美しい。とくに孤独をテーマにした話は文章が男前というか、しびれるような硬派でかっこいい言葉遣いの連続。これは翻訳自体の力もあると思います。
―自分が知らない言語の翻訳でも、やっぱり訳文の良し悪いというのはわかるものなんですか?
岸本:難しい問題ではあるんですが……たとえば、この『黒と白』の場合だったら、短編ごとに訳し方が明らかに違う。フォームが異なっているのがきちんと伝わってくる。
なにより、行ったこともないフィンランドの景色が浮かんできます。翻訳にとっていちばん大事なことは、読んでいる人の頭の中にイメージが湧くこと。それは、まず翻訳者が原文を読んで頭の中にしっかりイメージを構築しているから可能なことなんです。どんなに文章自体が正確だったとしても、訳者自身がイメージできていないものは読者にも伝わらない。
―なるほど。ご自身が翻訳の際に意識していることや気を付けてらっしゃることはありますか?
岸本:私が師匠から教わったのは、とにかく「直訳がベストである」ということ。本当に力のある作品は、他の言語に変換しても面白さは変わらないはずだから、奇を衒わず忠実に訳せばすべては伝わる、と叩き込まれまして。でもそれは逐語訳というのとは違うんです。直訳するためには、逆に字面からは離れる必要も、時にはある。
私は、翻訳家というのはラジオのようなものだと考えています。あくまで電波を受信して音を鳴らすだけで、自分自身のメッセージを発信するものではない。とはいえ良い音で鳴るためには、アンテナの感度とスピーカーの調子がものすごく重要になってくる。そういう部分のメンテナンスは常に怠らないようにしたいです。
―翻訳家=ラジオとは、面白いですね。
岸本:ちなみに、今回のインタビューに際して思い出したことがあって。私、中学生のときに「洋書が読んでみたい!」と思い立って、トーベ・ヤンソンの『THE SUMMER BOOK』という、英語に翻訳されたペーパーバックを買って読んでみたことがあるんです。
―『少女ソフィアの夏』(渡部翠=訳、講談社)という名前で日本語訳も出ている作品ですね。
岸本:「ムーミンの作者の本だし、きっと易しい内容だろう」と当て込んで手に取ったのですが、中学生には歯が立たず、3ページくらいで挫折してしまいました……。でも、それだけしか読んでないのにもかかわらず、そのときの印象はくっきり心に刻まれています。
というのも、主人公の少女がいきなり本人に向かって、「ねえ、おばあちゃんいつ死ぬの?」なんて聞いちゃう場面が出てくるんですよ(笑)。そもそも、おばあさんが落とした入れ歯を探す話から始まるというのもなかなかに不穏。「ほのぼの」とはほど遠いですよね。当時は、なんだかイメージと違うな、と感じたのですが、今回トーベ・ヤンソン作品を改めて読み直してみて腑に落ちました。
- プロフィール
-
- 岸本佐知子 (きしもと さちこ)
-
1960年神奈川県生まれ。上智大学文学部英文学科卒業。主な訳書にミランダ・ジュライ『いちばんここに似合う人』(新潮社)、ニコルソン・ベイカー『中二階』、ジャネット・ウィンターソン『灯台守の話』、リディア・デイヴィス『ほとんど記憶のない女』(以上白水Uブックス)、ジョージ・ソーンダーズ『短くて恐ろしいフィルの時代』(KADOKAWA)、ショーン・タン『夏のルール』、スティーヴン・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』(以上河出書房新社)。主な編訳書に『変愛小説集』『楽しい夜』(講談社)、『居心地の悪い部屋』(河出文庫)。編書に『変愛小説集 日本作家編』(講談社)がある。『ねにもつタイプ』(ちくま文庫)で2007年講談社エッセイ賞を受賞している。