ホラー映画やアメコミからインスパイアされた、ポップでカラフル、それでいてどこかグロテスクなユーモアも感じさせるイラストレーター / アーティストの我喜屋位瑳務(がきや いさむ)。YUKIやGREAT3、最近はSTUTSなど、ミュージシャンのアートワークやグッズ制作も手がける一方、2020年は東京・新宿のBギャラリーにて個展『GUINEA MATE』を開催。デジタルとアナログを織り混ぜた彼の独特な作風は、各方面で熱狂的な支持を集めている。
そんな我喜屋が「神」と崇め、ともに暮らしているのがモルモットのシモンちゃん。個展『GUINEA MATE』のコンセプトにも多大な影響を与え、主要作品のモチーフにもなったシモンちゃんは、我喜屋のSNSにもしばしば登場するなど、彼のファンにとってはお馴染みの存在だ。
北欧では、自然がより身近にあり、それが人々の幸福感につながっているとされる。そこで、今回は長いあいだ、パニック障害に悩まされていた我喜屋を助け、彼の生き方そのものまで変えた「モルモットとの生活」に焦点をあてる。モルモットの魅力とはどのようなもので、日々の暮らしをどう彩り、我喜屋の幸福感を高めているのか。我喜屋のアトリエを訪ね、「1人と1匹」の共同生活についてじっくりと話をうかがった。

沖縄県出身、東京在住のアーティスト。戦後のアメリカホラー映画やSF映画、アメコミなどに影響されたイラスト作品などで人気を得る。イラストレーター活動のほか、美術館での展覧会や芸術祭にも精力的に参加し、アーティストとしての活動を展開。
我喜屋にとってのアートは、見る者との「コミュニケーション」
―我喜屋さんの描くイラストは、子どものころに見たホラー映画やアメコミからの影響がとても大きいとお聞きしました。当時の我喜屋さんは、それらのどこに惹かれたのでしょうか。
我喜屋:ホラー映画はアイデアが好きなんですよね。例えばクリーチャーの造形とか、登場人物たちの殺され方とか(笑)。目覚めたきっかけは、子どものころにテレビで偶然見たアメリカのホラー映画『キャット・ピープル』(1942年 / ジャック・ターナー監督)だったんですけど、そのときはめちゃめちゃ怖かったんですよ。壁に隠れながら見ていたのですが、なぜか惹かれるものがあってのめり込んでいきました。
―「怖いもの見たさ」ってありますよね(笑)。アメコミはどんなきっかけでハマったのですか?
我喜屋:実際にアメコミを買うようになったのは、上京してイラストレーターになってからですね。コラージュの素材として収集したり、作品をつくるうえでのひらめきを求めたり。自分が好きなアメコミは1970年代、1980年代の古い印刷物のもの。線がちょっと外れている感じとか、色がちゃんと載っていない感じに愛着が湧くんです。アメコミの内容やキャラというよりは、絵柄の質感に惹かれたのだと思います。それに、アメコミ雑誌に掲載されているオモチャの広告もすごくいいんですよね。
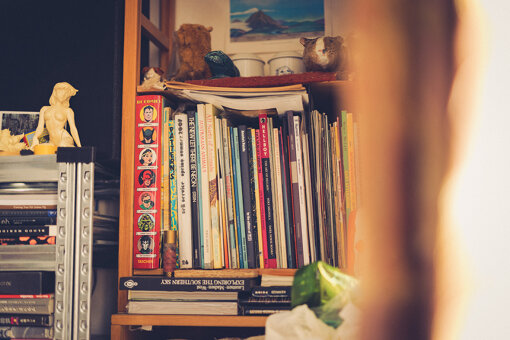
―アメコミのテクスチャーに惹かれるのは、我喜屋さんが沖縄出身であることも影響していますか?
我喜屋:それはあると思います。僕が沖縄に住んでいた子どものころは、アメリカの占領下だった時代のなごりがまだ色濃くあって。例えば軍向けに放送されているチャンネルで、アメリカのテレビアニメをよく見ていたんですよね。日本のアニメと違って色使いが独特だな、なんて思っていました。
―それに、我喜屋さんの作品に登場する女性は、いわゆる「かわいらしい」という印象ではなくて。もっと超然としているというか、強い意志を感じさせる人物が多いですよね。
我喜屋:あまり笑っている顔は描きたいと思わなくて。ちょっと目つきが悪いくらいのほうが人間っぽいと感じるんです。何かに対してつねに憤っている……それは自分自身が子どものころからそうだったからなのかもしれないですね(笑)。それと、女性の絵は寺田克也さん(岡山県出身のイラストレーター / 漫画家)の影響もあると思います。絵を描くことを始めたのも、寺田さんの絵に憧れたからなんです。
モルモットが登場する、我喜屋位瑳務の作品
―現在はアーティストとしての活動と、イラストレーターとしての活動を並行して行っているそうですが、それぞれの違いはありますか?
我喜屋:「コラージュ」という作風はどちらにも共通しているのですが、クライアントワークの場合はまず手描きの素材をコンピューターに取り込んでエディットしていくのに対して、アート作品の場合は逆の手順を踏んでいます。アメコミなど古い印刷物の線をスキャンし、それをバラバラにしたあとにコンピューター内で再構築していく。それをキャンバスに描き起こし、油絵で仕上げていくことが多いですね。クライアントワークの場合は「直し」もありますから、手描きよりもコンピューター内で仕上げていくほうが都合がいいんです。

―イラストレーターとしてはYUKIやGREAT3、最近はSTUTSなどミュージシャンのジャケットやグッズを描かれていますよね。その際に心がけているのはどんなことですか?
我喜屋:ありがたいことに、僕の場合は「自由にやっていいですよ」と言ってもらえることが多くて。もちろん、アーティストさんのイメージとか作品のテーマなど、ある程度の「縛り」はありますが、そのなかで本当に自由にやらせてもらっていますね。
我喜屋位瑳務が手掛けたSTUTS『Presence』ジャケット。ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』主題歌収録
―以前、我喜屋さんはご自身の作品のテーマについて「狂気と滑稽」とおっしゃっていましたよね。ちょっと視点がズレると「狂気」も「滑稽」に変わる、その描写はコーエン兄弟やポール・トーマス・アンダーソンといった映画監督たちの作品からの影響もあると。そのテーマは現在も変わっていないですか?
我喜屋:基本的には変わっていないのですが、あまりそれを言わないようにはしています(笑)。もうちょっとわかりやすいこと、例えば「コミュニケーション」なのではないのかなと思うんですよね。僕がつくったものをお客さんに見てもらい、どう感じるかで1つコミュニケーションが成り立つ。そこを大切にしていたのだなということに気づきました。
―作品のテーマ性を強く打ち出すことよりも、まず「見た人がどう感じるか」が重要なんですね。
我喜屋:あとは「世の中には、こんな絵もあるよ」ということを、もっと知ってほしい。それもあって最近は、毎日SNSで作品を発表しているんです。世の中に変わった絵を描く人はたくさんいるけど、どうしてもわかりやすい作品にばかり目が行きがちじゃないですか。そうしたわかりやすい作品とは異なるものを提案していきたいという意識もありますね。
モルモットが登場する、我喜屋位瑳務の作品
―そんな我喜屋さんはペットもわかりやすい犬や猫ではなく、モルモットのシモンちゃんと暮らしていますね。きっかけはどんなことだったのですか?
我喜屋:高校時代に、当時つき合っていた彼女と動物園にデートへ行ったんです。小動物との「ふれあいコーナー」があって、そこにいたモルモットがものすごくかわいかったんですよ。毛が寝癖みたいにぐしゃぐしゃになっていたりして(笑)。それで「ちょっとなかに入ってみようよ」と彼女に言ったら「気持ち悪いからイヤだ」と断られたのがすべての始まりですね。
―そのとき満たされなかった思いが募ってしまったのですね(笑)。
我喜屋:それから何年かして、テレビを見ていたら「モルモットはコミュニケーションが取れる動物」と紹介されていて。それでさらに興味が湧いてきたんですけど、実際に「飼おう」と思ったのはいまから8年前。友人とドライブしていたときに急に思い立ち、そのままペットショップへ立ち寄って連れて帰ってきたのが最初の子でした。シモンは4匹目です。
毎晩うなされる悪夢も、シモンで解消。一緒に暮らして深まったモルモット愛
―これまでのモルモットは、どんな名前だったんですか?
我喜屋:最初の子は「タッくん(本名は、ターミナル・コア)」で、次が「カンチ」、3番目が「プッチ」です。タッくんとカンチはアニメ『フリクリ』のキャラクター名から拝借して、プッチは『ミニオンズ』(アメリカのアニメ)に一瞬登場するネズミから、シモンはアニメ『天元突破グレンラガン』の主人公からそれぞれ名前をもらいました。

―高校時代から気になっていたモルモットを、実際に迎え入れてみてどうでした?
我喜屋:とにかくかわいいし、成長していくのが楽しくて仕方ないですね。小さいときって「ポップコーンジャンプ」という行動をするんですよ。気持ちが高ぶると、ブルブルしながらぴょんぴょん跳ぶんですね。それと、急にスイッチが入って部屋のなかを走り回る時間帯があって。大人になるにつれてだんだんやらなくなっていくんですけど、毎日それを見るのが楽しみでした(笑)。
―それぞれ性格も違うんでしょうね。
我喜屋:違いますね。1匹目のタッくんは凶暴で、そばに人間の手があると攻撃したくなるみたいで、自分はいつも傷だらけでした(笑)。シモンはポップコーンジャンプもそんなにやらなかったし、威嚇はするけど絶対に歯を当ててこない。すごく優しい子なんですよ。ほかのモルモットに対しても、人間が赤ちゃんをあやすようにピッタリくっついてあげているんです。ただ、ウンチはいままでの子のなかで一番臭い。それがまたたまらないんですけど(笑)。
―飼育の仕方はそんなに難しくないんですか?
我喜屋:最初にペットショップの方が丁寧に教えてくれたんです。言われるがままにケージなど、必要なものを買い揃えたし、モルモット自体そんなに手がかからないんですよね。
ただ体内に結石ができやすく、一度できてしまうと厄介なんです。メスの場合は石が小さければおしっこと一緒に出せるんですけど、オスは尿道が狭いので自然に出すのはかなり難しく、手術しなければいけません。小動物にとって、麻酔は命に関わるくらい大きな負担になるので、病気になってしまうとできることが限られているんです。

―予防が大切になってきますよね。モルモットに関する情報交換などもしていますか?
我喜屋:Twitterで繋がっている「モルモット仲間」がいるので、わからないことがあったらいろいろ尋ねています。みんな、本当に詳しいんですよ。しかも僕が個展をやると、シモンの差し入れを持ってきてくれる優しい人たちです(笑)。逆に、僕の影響でモルモットを飼い始めた方もいて、「どうしたらいいですか?」と飼い方の相談に来ることもありますね。
―シモンは、普段ずっとケージから出しているのですか?
我喜屋:外出するときはケージのなかに入れていますが、僕が家にいるときは基本的にケージの外に出していますね。だから歩くときは踏んだり蹴ったりしてしまわないよう、いつも気をつけています。
―さっき「モルモットはコミュニケーションをする動物」とおっしゃっていましたが、シモンとはいつもどんなコミュニケーションを取っていますか?
我喜屋:例えば僕が寝ようと思って布団に入ると、いつも僕の体の上に乗っかってくるんですよ。なぜかというと、牧草でできた大好物のビスケットが欲しいからなんですね。「じゃあ、食べる?」と言って、あげながら一緒に写真を撮ったりして。それは毎日の習慣ですね。あと、捕まえて匂いを嗅ぐ(笑)。とにかくモルモットの匂いが好きなんです。「モル吸い」という言葉があるくらい、身体がいい匂いで。

―「猫吸い」「犬吸い」ならぬ、「モル吸い」ですね(笑)。
我喜屋:あとは「前歯アタック」というコミュニケーションもあります。手を出したときに、「近づくな!」と威嚇して前歯を当ててくるんですけど、それがかわいくて(笑)。でも、シモンが絶対に人の手を噛まないのは、「噛んだら相手が痛い」というのをわかっているからみたいで。それから言葉もちゃんと覚えますね。「ビスケット」も「食べる?」も理解しているし、おそらく自分の名前もわかっています。あと、シモンはうれしいときに頭をバタバタするんですけど、それはいままでのモルモットはしなかったシモンの個性なんですよね。
―ペットとの暮らしを負担に感じたり、辛くなったりしたことはありますか?
我喜屋:まったくないですね。さっき、タッくんは凶暴だったと言いましたが、僕はモルモットには何をされても平気です。たとえ大事なものを噛みちぎられたり破壊されたり、布団におしっこされたりしても(笑)。
―僕も犬を飼っていて、我喜屋さんと同じ心境なんですよね(笑)。よくペットに腹を立てる人がいますが、その気持ちがわからなくて。そもそも期待していないのかなと思います。自分が注ぐ愛情に相手が応えようが応えなかろうが、そこは大した問題じゃないし、動物はそこに存在しているだけで尊いんですよね。
我喜屋:わかります。それが「無償の愛」ということなんですかね。モルモットには反抗期があって、その時期になると急に素っ気なくなるんですけど、それでも僕は追いかけています(笑)。
―Twitterにも「見返りを求めないのが愛」と投稿されていましたが、心から同意します。
我喜屋:自分でもこんなにモルモットを大好きになるとは思わなかったです。毎日幸せを感じるんですよ。僕はいつも悪夢を見て目覚めるんです。もううんざりするくらい毎晩見ているんですけど、起きたらシモンがいるから、それでプラマイゼロです(笑)。コロナになって、人と会えなくなってずいぶん経ちますけど、僕は「モルモット」と「オンラインゲーム」に助けられて生きていますね。
無理をせず、自分を肯定する。モルモットに教わった本来の動物的な生き方
―動物と暮らしていると、どうしても最後は死に直面するわけですが、これまで一緒に暮らしてきた3匹を見送った経験をどう受け止めていますか?
我喜屋:最初の子が病気になったときはとにかく看病が大変だったのですが、それすらも幸せな気持ちで看病できたんです。すぐに粗相してしまうようになって、そのたびにモルモットの体を洗わなければならなかった。ものすごく暴れていましたが「苦」など微塵もなくて。病気は心配でしたけど、その時間さえ尊いと感じながら世話をしていましたね。ただ、プッチの最後は看取れなかったんです。病院に入院させた翌日の朝に死んでしまって。そのことがずっと引っかかっていて、いまでも毎日思い出してしまいますね。誰にも看取られないままで、「寂しかっただろうな」って。
―ペットの死を前にして、「こんな思いをするなら、もう二度と飼いたくない」と思う人もいますよね。
我喜屋:僕にそれはなくて、これからもずっと飼い続けようかなと思っていますね。いままでの子への思いを受け継いで、また新しい子と暮らしていきたいという気持ちでいます。僕は、モルモットが亡くなったら1つずつタトゥーを肩に入れるようにしているんですよね。

―ちなみにモルモットと暮らすようになって、ご自身のクリエイティブに変化はありましたか?
我喜屋:心に余裕ができましたね。自分は締め切りに追われるのが向いていなくて、しんどいことが多かったんですけど、モルモットと一緒にいるとそれが緩和されるんです。疲れたらシモンのところへ行けば癒されるし(笑)。
―2020年に開催された個展『GUINEA MATE』では、モルモットをモデルにしたガレージキットを製作されていましたよね。
我喜屋:はい。胸に「PANiC DiSORDER」(パニック障害)と彫っているのですが、僕が10年以上患っていたパニック障害を供養するための「お地蔵さん」として制作しました。『GUINEA MATE』というのは、モルモットを「神」と崇める架空の宗教の名前なんです。
僕は、この世界に「救いの神」など存在しないと思っているんですね。そんなものがもし本当にいるなら、とっくの昔に戦争も貧困もなくなっているわけで。だったら既存の宗教や神様に頼るのではなく、一人ひとりがオリジナルの宗教や神様をつくって自分を救えばいいと思うんです。
『GUINEA MATE』のガレージキット
―個展『GUINEA MATE』には、そんなテーマがあったのですね。そうした世界の捉え方、ものの見方はモルモットと暮らすようになったからこそ思いついたのですか?
我喜屋:そう思います。それから「人に依存しないほうがいい」ということも、モルモットから学びました。人間にはそれぞれの事情があって、人と人とが関わり合うとそこには必ず「軋轢」や「葛藤」が生じてしまう。でも、動物からそれを感じないんですよね。損か得かで動いていない。つくづく「神」だなあと思います(笑)。

―お話をうかがっていて、それって「推し」に対する気持ちにも近いのかなと思いました。ペットを「神」と設定して無償の愛を注ぐことと、「推し」に惜しみない愛情を注ぐことは、似ているような気がします。
我喜屋:ああ、たしかに似ているかもしれないですね。救いを求めるのは「神」ではなく、「推し」でもいいと思います(笑)。
―『GUINEA MATE』には信条が108個あるとTwitterに投稿されていましたよね。例えば「疲れたらすぐ休む」「約束はなるべくしない」「自分だけを信じる」などは、モルモットと暮らすようになって実感されたことも多いのでしょうか。
我喜屋:いまって自分を責めたり、人に合わせて無理をしたりする人がすごく多いなと思っていて。そうではなく、完全に自分を肯定すればいいんじゃないかなと思い始めたんです。それって本来の動物的な考え方なのかなと思います。ほとんどの動物は、おそらく自分を責めたり無理したりすることってないじゃないですか。なのでおっしゃるように、シモンとの暮らしから学んでいる部分が多いと思います。
『GUINEA MATE』の信条、108箇条の一部
―動物って基本的に食べているか寝ているか遊んでいるかですもんね。その様子を見ていると「ほかに何が必要というのだろうか?」と考えてしまします。
我喜屋:本当にそう思います。元気でさえいれば、あとはもう何もいらない。僕は、40歳を超えたあたりから生きるのが楽になったんですよ。仕事も人間関係も「無理をしない」と決めたので。そう思えるようになったのは、いままでずっと悩みながらもがき続けたからかもしれないし、モルモットが僕をその境地まで運んでくれたからかもしれない。あるいは両方あったからかもしれないなと思うんですよね。
―最後にあらためてお聞きします。我喜屋さんにとってモルモットは、どんな存在ですか?
我喜屋:モルモットとは「神」でもあり「友人」でもあり、「家族」「恋人」、そして「王」でもある。本当にいろいろなことを教えてくれる、美しい存在ですね。

- プロフィール
-
- 我喜屋位瑳務 (がきや いさむ)
-
沖縄県出身、東京在住のアーティスト。戦後のアメリカホラー映画やSF映画、アメコミなどに影響されたイラスト作品などで人気を得る。イラストレーター活動の他、美術館での展覧会や芸術祭にも精力的に参加し、アーティストとしての活動を展開。モルモット、シモンと暮らしている。



